人が亡くなった後に残された物を整理する「遺品整理」。
言葉ではシンプルに聞こえるかもしれませんが、実際にその場面に立たされると、想像以上に大変だと感じる方が多いのが現実です。
「いつかはやらないといけないこと」と分かっていても、心の準備も、体の準備も追いつかない。
この記事では、そんな遺品整理の大変さと向き合い方、そして少しでもラクに進めるためのヒントをご紹介します。
遺品整理が「大変」と言われる理由
1. 物の量がとにかく多い
故人が暮らしていた家には、衣類や家具、家電、書類、雑貨、写真など、何十年分もの生活の痕跡が詰まっています。
「たくさんあるけど、あとでまとめて片付けよう」と思っていたものが、気づけば押し入れや引き出しにパンパンに詰まっていた…。
そんな状況に直面すると、どこから手を付ければいいか分からなくなってしまいます。
2. 感情の整理が追いつかない
遺品整理は単なる物の片付けではありません。一つひとつの物に故人との思い出が詰まっており、それを手に取るたびに感情があふれ出すことも。
「これは捨てていいのか?」
「思い出があるから残したいけど…」
そんな気持ちとの葛藤に時間も心も削られてしまいます。
3. 体力的にも時間的にも負担が大きい
一人でやろうとすると、丸一日かかっても数部屋の片付けが精一杯ということも珍しくありません。
特に高齢者のご家族が遺品整理を担う場合、重たいものを動かしたり、ゴミを仕分けたりする作業が大きな負担になります。
また、仕事や家庭がある中で遺品整理の時間を作るのも簡単ではありません。
実際に遺品整理を経験した人の声
「母が亡くなった後、遺品整理を妹と二人で行いました。思い出の品が多く、どれも捨てるのがつらくて、結局何度も家に通うことに…。気持ちの整理にも時間がかかり、本当に大変でした。」
「遠方に住んでいるので、仕事の合間に実家に通って整理しました。処分のルールも地域で違い、粗大ごみの手続きなども手間でした。」
こうした声は少なくありません。
遺品整理をスムーズに行うためのポイント
1. 焦らず、計画的に進める
いっぺんにすべてを終わらせようとせず、「今日はこの部屋だけ」「まずは衣類から」など、少しずつ進めるのがおすすめです。
また、遺族が複数いる場合は、誰がどの部分を担当するか話し合って分担しておくとスムーズです。
2. 「いる物・いらない物」の基準を決めておく
「保管する物」「処分する物」「迷っている物」など、あらかじめカテゴリーを作って仕分けしていくと作業がはかどります。
迷うものは“保留ボックス”に入れて、後から判断するのもOKです。
3. 専門業者への依頼も選択肢に
時間や体力、精神的な負担を考えると、遺品整理の専門業者に依頼するのも賢い選択です。
不用品の処分、形見分け、掃除まで一括で行ってくれる業者もあり、家族の負担を大幅に軽減できます。
料金は業者や物量によって異なりますが、1Kの部屋で5万〜10万円ほどが目安。見積もりは無料のところが多いので、まずは相談してみるのもよいでしょう。
生前整理という考え方も
最近では、「自分の死後、家族に迷惑をかけたくない」という思いから、生前整理を行う方も増えています。
元気なうちに不要なものを処分し、本当に大切なものだけを残すことで、自分の人生を見つめ直すきっかけにもなります。
また、家族にとっても遺品整理の負担を軽減できるため、双方にとってメリットのある行動です。
まとめ:遺品整理は“気持ち”と“時間”の整理
遺品整理は、単なる「片付け」ではありません。
そこには、故人との別れや、思い出との向き合い、家族間の関係性など、さまざまな感情が交差する繊細な作業です。
だからこそ、焦らず、丁寧に進めること。
そして、自分たちだけで抱えきれないと感じたときは、専門家の手を借りることも大切な選択肢です。
「遺品整理って大変だな」と感じているあなたは、決して一人ではありません。
少しずつ、できることから始めてみませんか?

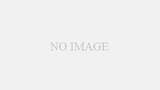
コメント